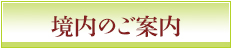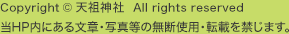| 1月1日 午前0時より | 神楽殿にて神楽舞の奉納 |
|---|
| 1月1日 午前11時より | 元旦祭 |
|---|
| 初詣は氏神様から 初詣は氏神様から御参拝しましょう。(東京都神社庁が制作した動画です。当神社で撮影しました。) |
| 1月14日 午前10時より | お焚き上げ(天候により延期することがあります) |
|---|
古いお札やお守りなどは、境内に長期間置くのは防火上大変危険ですので、1月7日から13日にお持ち下さい。
お焚き上げは、お札類に限って行います。(お人形はお受けできませんのでご遠慮ください)
有害なダイオキシンは物を燃やすと発生します。野外焼却によるダイオキシンの発生を抑えるため、お正月のお飾りは、設備の整った清掃工場で焼却するよう、可燃ゴミに出してください。
お正月のお飾りは、年神様が降りてくるための目印です。また、年神様は、どんど焼きの煙に乗ってお帰りになると言われています。神社ではお正月のお札とご一緒に年神様の御幣をお授けしています。
お焚き上げには年神様の御幣のみをお納め下さい。皆様のご理解とご協力をお願い致します。
| 6月 夏至の日 午後4時より | 夏越の大祓 |
|---|
| 10月 第1の日曜とその前日の土曜 | 例大祭(大祭式は、日曜の午前10時に斎行致します) |
|---|
鎮守様とは、地域の人たちが地域の土地を護(まも)るためにお祀(まつ)りした神様です。
天祖神社は、明治時代には村社として地域をお護りしてきました。鎮守様のお祭りには学校がお休みになり、村社天祖神社に感謝のお詣(まい)りを致しました。
お祭りには、鎮守天祖神社のご守護に感謝し、お詣りを致しましょう。
| 12月 冬至の日 午後4時より | 年越の大祓 |
|---|
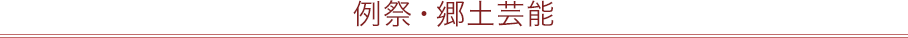
江戸時代には9月26日(旧暦)と定められておりましたが、明治の改暦後9月は雨が多く、10月2日〜3日に変更されました。しかし最近では、ご時勢に例(なら)い、10月始めの日曜日となり、前日は宵宮(よみや)として2日間行なわれております。
お祭りといえば祭囃子(まつりばやし)ですが、当社には「経堂流(きょうどうりゅう)」といわれている「安宅囃子(あたかばやし)」が伝えられています。この名前は曲目の「安宅崩(あたかくず)し」に由来していますが、テンポが速く威勢(いせい)のいい囃子です。
詳しくは安宅囃子保存会のホームページをご覧ください。


 |
元旦並びに例大祭当日に神楽舞が奉納されます。 古来日本人は恵みを与えてくれる神々に対し、感謝と祈りを捧げ、神楽舞を神前に奉納してきました。 神社の祭りにおいて神楽とは、天岩戸の「天鈿女命(あめのうずめのみこと)」の神話に由来し、神楽を神前で舞うことにより、神慮は慰められ、神霊はあるべき御座(みくら)にとどまると考えられています。 神意に適う神前神楽を神前に納めることができた時、神慮は慰められ、神楽を通じて神の恵みが人々に降り注がれます。 「神は人の敬いによりて威を増し、人は神の徳によりて運を添ふ」
(御成敗式目より)
という善なる循環を生み出すもの、それが神社における神楽、神前神楽舞なのです。
|
|---|
![[経堂鎮守]天祖神社](images/logo.jpg)